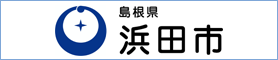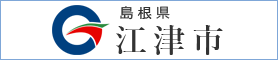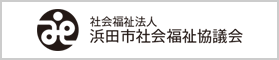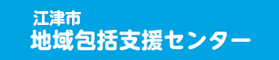ここから本文です。
介護保険
各サービス共通
介護現場におけるハラスメント対策
指定介護サービス事業者は、適正なサービス提供を確保する観点から、職場において行われるハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化などの必要な措置を講じなければならないこととされています。
実態の把握及びハラスメント対策の検討・実施、事業所内の研修の実施等の必要な措置を講じるにあたっては、下記掲載資料等を必要に応じて活用してください。
業務継続計画
業務継続計画(BCP)について
介護サービスは、利用者やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
令和3年4月の制度改正で、必要なサービスを継続的に提供するため、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図ることが出来るよう「業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)」を策定することが義務付けられています(令和6年3月31日までは経過措置)ので、厚生労働省が示したガイドライン等を踏まえ、事業所の実情に沿った実効的な計画の策定をお願いします。
事故報告
介護サービス等の提供に係る事故の状況
処遇改善加算
令和5年度処遇改善加算の実績報告書の提出について
令和5年度に「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」または「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所におかれましては、令和6年7月31日までに実績報告書の提出が必要となります。
(1)注意事項
- 実績報告で賃金改善額が加算額以下の場合、加算要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。
- 実績報告書は、令和5年度の計画書作成単位で提出してください。
- 実績報告書に記載する「加算区分」については、令和5年度の計画書と同じ加算区分で提出してください(※令和6年度に区分の変更があった事業所は特にご注意ください)。
- 加算は、介護職員の賃金改善(賃金改善により増加した法定福利費事業主負担分を含む)にしか充てることができません。
- 賃金改善実施期間内に介護職員への支給を終えてください。
- 加算に係る支出と実際に介護職員等の賃金に充てたことが分かる書類を作成し、実績報告後2年間以上は保存しておいてください(過誤調整を行う場合は、最大5年遡ります)。
(2)提出書類
(3)提出先
- 事業所所在地ごとの提出先に提出してください。(当組合への提出は当組合圏域内の地域密着型及び総合事業のサービス事業所となります)
- メールにより提出の際は、原則Excelファイルのまま送付してください。
- 法人単位等で複数事業所を一括して届出する場合は、各事業所の指定権者(各介護保険者)に対して提出が必要です。その際の提出方法については、各指定権者へご確認ください。
令和6年度の処遇改善加算等にかかる計画書の提出について
令和6年度において加算を算定する事業所については、「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)」(以下、「計画書」という。)を提出していただく必要があります。
また、加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更」する場合に限り、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。
(1)注意事項
- 届出にあたっては制度概要資料等をご確認いただき、記載内容の根拠となる資料等を適切に保管してください。
- 必ず設定した賃金改善期間内に当該年度の加算受給総額を上回る賃金改善を行ってください。(賃金改善実施期間終了月までに処遇改善に係る支払いを完了してください)
(2)提出書類
下記のリンク先から必要な様式を入手してください。
(3)提出先
- 事業所所在地ごとの提出先に提出してください。(当組合への提出は当組合圏域内の地域密着型及び総合事業のサービス事業所となります)
- メールにより提出の際は、原則Excelファイルのまま送付してください。
- 法人単位等で複数事業所を一括して届出する場合は、各事業所の指定権者(各介護保険者)に対して提出が必要です。その際の提出方法については、各指定権者へご確認ください。
介護給付費過誤申立
負担限度額認定照会票
関連様式集
介護保険事業者向け研修案内
介護人材キャリアアップ事業
介護保険に携わる人材の育成とサービスの質の向上を図るため、介護従事者のキャリアアップに要する費用の一部を補助いたします。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準等を満たすことができなくなる場合等が想定されます。
この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いが可能とされておりますので、次の内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ
当該取扱いの第16報までをサービス別にまとめたものです。(厚生労働省HP)
浜田地区広域行政組合が発出した取扱い
ケアマネジメントに関する基本方針
- 1
- 介護保険法の基本理念
介護保険法では、その目的等について以下のとおり定められています。
介護保険法
(目的)
- 第1条
- この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護保険)
- 第2条
- 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
- 2
- 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
- 3
- 第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
- 4
- 第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
(国民の努力及び義務)
- 第4条
- 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
- 2
- ケアマネジメントの基本方針
浜田地区広域行政組合では、「介護予防支援に関する基本方針」及び「居宅介護支援に関する基本方針」を、それぞれ以下のとおり条例の中に定めています。
浜田地区広域行政組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
(基本方針)
- 第1条の3
- 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
- 2
- 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
- 3
- 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
- 4
- 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、浜田地区広域行政組合(以下「組合」という。)、地域包括支援センター(法第 115 条の 46 第1 項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38 年法律第 133 号)第20 条の 7 の2 第1 項に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123号)第51 条の 17 第1 項第 1 号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
- 5
- 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
- 6
- 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
浜田地区広域行政組合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
(基本方針)
- 第1条の2
- 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
- 2
- 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環環等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
- 3
- 指定居宅介護支援事業者(法第46 条第 1 項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8 条第 24 項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41 条第 1 項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
- 4
- 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、浜田地区広域行政組合(以下「組合」という。)、法第115 条の 46 第1 項に規定する地域包括支援センター(いか「地域包括支援センター」という。)、老人福祉法(昭和38 年法律第133 号)第20 条の 7 の2 に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58 条第 1 項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123 号)第51 条の 17 第1 項第 1 号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
- 5
- 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
- 6
- 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
- 3
- 将来像
浜田地区広域行政組合 第9期介護保険事業計画では、本圏域の目指すべき姿を以下のとおり掲げています。
- (1)住みなれた家で暮らし続ける
生活機能低下や疾病により要介護状態に陥らないよう、病気の重症化予防のための運動や食事などの健康的な生活習慣の確立や健康管理、介護予防に努める仕組みづくり。
予期せぬことで、心身の状態変化があっても様々な居宅サービスの利用、かかりつけ医や多職種の医療介護従事者等の連携、さらには、地域の支えあいにより、在宅生活を維持し続ける仕組みづくり。
(在宅医療・介護の連携強化、認知症になっても暮らしやすい地域づくりなど) - (2)なじみの関係で暮らし続ける
認知症や医療依存度が高いことによる影響、また家族環境等により、やむを得ない状況変化によって施設等へ入所した場合においても、なじみの関係を構築し、安易な居所変更をしなくてもよい仕組みづくり。
(多様な住まいの充実、看取りまでできる体制整備など) - (3)圏域内で暮らし続ける
医療処置の必要性が高い高齢者であっても、できる限り圏域内の施設にとどまる仕組みや体制づくり。
施設待機者であっても、在宅で介護できるような医療・在宅サービスの充実。
在宅で介護する家族などへの支援や、地域資源の活用による見守りなどの充実。
(介護医療院などの施設の整備、看護小規模多機能型居宅介護サービスなどの医療系介護サービスの強化、家族介護支援の充実など)
- 4
- 計画の基本目標
- 1 地域共生社会と地域包括ケアシステムの実現
- (1)地域共生社会の実現に向けた取り組み
- (2)地域特性を踏まえた地域包括ケアの充実
- (3)地域包括支援センターの体制強化
- (4)地域包括支援センターの役割
- (5)高齢者の住まいを中心とした生活基盤の整備
- 2 介護予防・健康づくり施策の充実・推進
- (1)介護予防事業の推進
- 3 地域活動と連携した生活支援体制の充実
- (1)高齢者の生きがいと暮らしの向上
- (2)生活支援体制の充実と担い手の育成
- 4 認知症施策と権利擁護の推進
- (1)認知症への理解と支援体制
- (2)高齢者等の権利擁護の推進
- 5 医療・介護連携の推進
- (1)医療・介護連携体制の強化
- (2)リハビリテーションの推進
- 6 介護人材の確保と質の向上
- (1)介護サービスの質の向上
- (2)地域人材の活用
- (3)最新技術を導入した業務改善と効率化の促進
- 5
- ケアマネジメントにあたって
本圏域の目指すべき姿を実現するため、ケアマネジメントの一連のプロセスにおいては、「高齢者の自立」「地域での支えあい」「住みなれた地域での暮らし」が実現されるよう、対象者にアセスメントを行い、ケアプランを作成することが重要になります。
また、介護予防ケアマネジメントにおいては、事業対象者及び要支援認定者が要介護状態等となることを予防するため、対象者にアセスメントを行い、心身の自立性向上を見込めるプランを作成し、総合事業やその他の適切な事業等を利用することで生活機能の維持・向上が図られるように援助することが求められます。
介護支援専門員の皆様におかれましても、本指針等をご確認いただき、本圏域の将来像実現に向けて、更なる取組を進めていただきますようにお願いいたします。
浜田地区広域行政組合 第9期介護保険事業計画
- 地域共生社会と地域包括ケアシステムの実現(43頁~48頁)
- 介護予防・健康づくり施策の充実・推進(49、50頁)
- 地域活動と連携した生活支援体制の充実(51、52頁)
- 認知症施策と権利擁護の推進(53頁、54頁)
- 医療・介護連携の推進(55頁)
- 介護人材の確保と質の向上(56頁~58頁)
保険者が発出した通知
 平成30年12月14日 指定居宅介護支援における「退院・退所加算」の算定について(PDF)
平成30年12月14日 指定居宅介護支援における「退院・退所加算」の算定について(PDF) 平成30年9月10日 指定居宅介護支援の具体的取扱方針に基づく居宅サービス計画の届出について(PDF)
平成30年9月10日 指定居宅介護支援の具体的取扱方針に基づく居宅サービス計画の届出について(PDF) 平成30年 4月24日 訪問型サービスA(緩和型)とサービス提供責任者を兼務する場合の取り扱いについて(PDF)
平成30年 4月24日 訪問型サービスA(緩和型)とサービス提供責任者を兼務する場合の取り扱いについて(PDF) 平成30年 3月16日 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(PDF)
平成30年 3月16日 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(PDF) 平成28年 9月 5日 訪問介護における通院等乗降介助に係る算定基準について(PDF)
平成28年 9月 5日 訪問介護における通院等乗降介助に係る算定基準について(PDF) 平成28年 2月23日 介護保険における適切な福祉用具貸与について(PDF)
平成28年 2月23日 介護保険における適切な福祉用具貸与について(PDF) 平成26年 5月15日 転入による指定地域密着型サービス事業所への入居等要件について(PDF)
平成26年 5月15日 転入による指定地域密着型サービス事業所への入居等要件について(PDF)
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業の条例、要綱
 浜田地区広域行政組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和6年4月1日施行)(PDF)
浜田地区広域行政組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和6年4月1日施行)(PDF) 浜田地区広域行政組合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(令和6年4月1日施行)(PDF)
浜田地区広域行政組合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(令和6年4月1日施行)(PDF) 浜田地区広域行政組合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年4月1日施行)(PDF)
浜田地区広域行政組合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年4月1日施行)(PDF) 浜田地区広域行政組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(令和6年4月1日施行)(PDF)
浜田地区広域行政組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(令和6年4月1日施行)(PDF) 浜田地区広域行政組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(令和6年4月1日施行)(PDF)
浜田地区広域行政組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(令和6年4月1日施行)(PDF) 浜田地区広域行政組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和6年6月1日施行)(PDF)
浜田地区広域行政組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和6年6月1日施行)(PDF)
令和6年度介護報酬改定に伴う体制届等の届出について
令和6年4月1日適用分の提出期限は、令和6年4月15日(月)です。
「加算変更一覧」をご確認の上、期限内に提出いただきますようお願いします。
- ※
- 令和6年6月1日適用分の提出期限については、通常通りです。
なお、令和6年4月1日適用分の提出に併せて提出しても差し支えありません。4月1日改定分に関しては、以下の「加算変更一覧」(届出がない場合の移行状況)を参考にしてください。
一覧はサービス種別ごとのリストとなっていますので、該当のサービス種別をご確認ください。
留意事項
- 令和6年3月31日まで経過措置とされていた「虐待防止に係る措置」及び「業務継続計画の作成」については、
「高齢者虐待防止措置実施の有無」
「業務継続計画策定の有無」の項目が新設されていますが、届出がない場合「2.基準型」で台帳登録されます。
その他の項目について、現行の体制の届出状況に変更がない場合は、届出を省略することができます。 - 新設の加算については、届出がない場合「1.なし」で台帳登録されますので、算定される場合は必ず届け出てください。
- 現行の体制届出状況を踏まえたうえで、一覧表で届出の必要有無を必ずご確認ください。